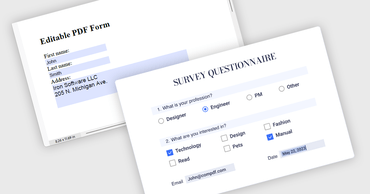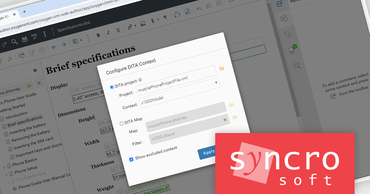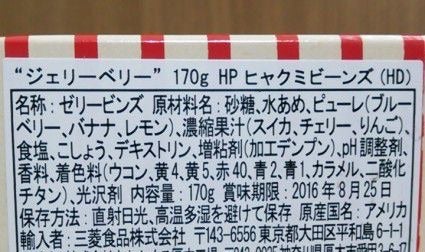2019 日々の聖句 1月27日㈰~2月2日㈯
2019 日々の聖句 1月27日㈰
聖言にしたがい我をささへて生存しめたまえ。わが望につきて恥なからしめたまえ。(詩119:116)
キリストの言葉:視よ、我なんぢの前に開けたる門を置く、これを閉ぢ得る者なし。汝すこしの力ありて、我が言を守り、我が名を否まざりき。(黙示録3:8)
私の黙想:
文語訳を読んでいると漢字と送り仮名とが、かなり自由に使われていることに気がつく。例えば今日の聖句「聖言に従い我を支えて生存しめたまえ。我が望につきて恥なからしめたまえ」と書くことも可能である。おそらく、礼拝での聖書朗読を配慮しているのであろう。
今日の聖句、新共同訳は面白い。「あなたの仰せによりすがらせ、命を得させてください。わたしの望みを裏切らないでください」「よりすがらせ」、「裏切らないでください」。詩人は謙遜を超えて、もう「卑下」の状態である。私たちの信仰とはそんなものだろうか。口語訳では、「あなたの約束にしたがって、わたしをささえて、ながらえさせ、わが望みについて恥じることのないようにしてください」。ついでに協会訳を開くと、「私が生きていけるように、あなたの仰せに従って私を支えてください。自分の望みについて、私が恥じ入ることがないようにしてください」と、見事に文語訳、口語訳を回復している。これなら、私たちの許容範囲である。
2019 日々の聖句 1月28日㈪
歓喜(よろこび)と救いとの聲は正しき者の幕屋にあり。主の右の手は勇ましき動作(はたらき)をなしたまう。主の右の手は高く上がり、主の右の手は勇ましき動作(はたらき)をなしたまう。(詩118:15~16)
汝ら常に主にありて喜べ、我また言ふ、なんぢら喜べ。(フィリピ4:4)
私の黙想:
この短い聖句に、「右の手」という言葉が3回も繰り返されている。これはどの訳でも同じである。特に主の右の手は「勇ましい」という言葉が2回繰り返されている。ここで用いられている「動作」を「はたらき」と読むのには、現代語では違和感がある。しかしそれが明治・大正時代の言葉なのであるから仕方がない。
「右の手」、神に右も左もあるのか、疑問は残るが単純に考えて、力強さの象徴であろう。
神が動けば、神は意味なしに動くことはないし、動けば何かが起こる。
この言葉口語訳では率直に「働き」、新共同訳では「御力」、協会訳では単に「力」と訳している。この差異は面白い。力とは発揮されて働きとなるが、働かなくても力は力である。
2019 日々の聖句 1月29日㈫
イスラエルの企望(のぞみ)なる者、その艱(なやめ)るときに救うたまう者よ、汝いかなれば此地に於て他邦人(ことくにびと)のごとくし、一夜寄宿(ひとりやどり)の旅客(たびびと)のごとくしたまうや。(エレミヤ14:8)
今われらは鏡をもて見るごとく見るところ朧(おぼろ)なり。然れど、かの時には顏を對(あわ)せて相見ん。(1コリント13:12)
私の黙想:
ここでは「他邦人(ことくにびと)」という珍しい言葉が出てくる。通常は「異邦人」である。時間の関係で「他邦人」という言葉と「異邦人」という言葉との詳細について調べていない。ただ、残念ながら口語訳以降は使われていない。
口語訳は「異邦の人」、新共同訳では「この地に身を寄せている人」と訳している。
そこで、私なりに勝手に考えると「異邦人」と「他邦人」とは確かに違いがある。日本語でも「異国人」「外国人」おまけに「ガイジン」といういい方もある。人間と人間との関係おいて、「異」と「他」、あるいは「外」との違いは何か。その説明は不要であろう。
協会訳で「希望」が文語訳では「企望」という漢字が当てはめられているのは面白い。これは単なる希望ではなく、その希望そのものを「企画」している者という意味であろう。その神がイスラエルにおいて「ガイジン」のような在り方をしている。
1月20日から始めた文語聖書によるローズンゲン、ちょうど1週間です。ぜひ皆様方のご意見をを伺いしたいと思います。
2019 日々の聖句 1月30日㈬
主は我儕(われら)を、御心に記(と)めたまえり。(中略)われらを惠みたまわん。(詩115:12)
汝らの名の天に録されたるを喜べ。(ルカ10:20)
私の黙想:
新共同訳ではかなり長い文章を短縮しているので、文語訳でも短縮しておく。「御心に記(と)め」を新共同訳、口語訳では「み心に留め」、協会訳では「思い起こし」、ほとんど同じようでないか違いがある。
これらの言葉を比較しながら、ルカ福音書の十字架上のイエスの言葉を思い起こす、というより心に留める。共に十字架上にいた悪人の一人が「イエスよ、あなたの御国にいらっしゃれたら、私のことを思い出してくださいますように」(23:42、田川訳)、これに対するイエスの言葉は省略しておく。これを文語聖書では「イエスよ、御国に入り給うとき、我を憶え給え」。
「み心に留める」「思い起こす」「思い出す」は、聖書を読む場合の鍵となる単語である。
2019 日々の聖句 1月31日㈭
妄(みだ)りに言を出し、劍をもて刺が如くする者あり。されど智慧ある者の舌は人を癒やす。(箴言12:18)
また船を見よ、その形は大(おおき)く、かつ激しき風に追はるるとも、最小(いとちいさ)き舵にて舵人の欲するままに運(まあ)すなり。斯くのごとく舌もまた小(ちいそ)きものなれど、その誇るところ大なり。視よ、いかに小(ちいさ)き火の、いかに大なる林を燃すかを。(ヤコブ3:4~5)
私の黙想:
新共同訳では、「軽率なひと言が剣のように刺すこともある。知恵ある人の舌は癒やす」。協会訳は解説の文章のようである。「あたかも剣で刺すかのように軽率に語る語る者がいる。知恵ある人の舌は癒やしを与える」。
この格言、このようにも言えるのではないだろうか。「軽率なひと言は人を殺し、知恵ある言葉は人を生かす」。少々、投げやりな黙想。仕方がない。
2019 日々の聖句 2月1日㈮
我が王よ、我が神よ。 我が號呼(さけび)の聲を聞きたまえ。我、汝に祈ればなり。主よ、朝(あした)に我が聲を聞き給わん。我、朝(あした)に汝の為に備えして俟望むべし。(詩5:2~3)
我、信ず、信仰なき我を助け給え。(マルコ9:24)
私の黙想:
2月初めの聖句は、まさに現在の私の祈りである。「明日を俟つ」。読み方によっては、主ご自身の応答に起き超える。「我、朝(あした)に汝の為に備えして俟望むべし」。
口語訳、「主よ、朝ごとにあなたはわたしの声を聞かれます。わたしは朝ごとにあなたのためにいけにえを備えて待ち望みます」。
新共同訳、「主よ、朝ごとに、わたしの声を聞いてください。朝ごとに、わたしは御前に訴え出てあなたを仰ぎ望みます」。
協会訳、「朝が来る度に、あなたに向かって身を整え、待ち望みます」。
祈祷書訳、「主よ、朝ごとにあなたはわたしの祈りを聞き、・・・・」。
2019 日々の聖句 2月2日㈯
汝、踴躍(おどり)をもて、我が哀哭(なげき)に変え、我が麁服(あらたえ)を解き、歓喜(よろこび)をもて我が帶としたまえり。(詩30:12)
その中の一人、おのが醫されたるを見て、大聲に神を崇めつつ歸り来たり。(ルカ17:15)
私の黙想:
「麁服(あらたえ」とは「荒妙」とも書き、粗い布織りの粗末な着物を意味する。この聖句を新共同訳では「あなたはわたしの嘆きを踊りに変え、粗布を脱がせ、喜びを帯としてくださいました」。
この詩はダビデが宮殿の建立式で歌ったとされる。「麁服」が質素の宮殿を意味し「帯」が新しい宮殿を象徴するのであろう。
紀元前1000年頃、ダビデが王位に就いたときに、この地方を支配するために有利な場所として名もなき丘の上に砦のような粗末な基地を造り、拠点とした。それが元々のエルサレムである。それはまさに「前線基地」に過ぎなかった。ダビデの地位が確立するに従って「エルサレム」は人口も増え、立派な都になった。そのときダビデは粗末な砦を改築し宮殿とした。
2019 日々の聖句 1月27日㈰
聖言にしたがい我をささへて生存しめたまえ。わが望につきて恥なからしめたまえ。(詩119:116)
キリストの言葉:視よ、我なんぢの前に開けたる門を置く、これを閉ぢ得る者なし。汝すこしの力ありて、我が言を守り、我が名を否まざりき。(黙示録3:8)
私の黙想:
文語訳を読んでいると漢字と送り仮名とが、かなり自由に使われていることに気がつく。例えば今日の聖句「聖言に従い我を支えて生存しめたまえ。我が望につきて恥なからしめたまえ」と書くことも可能である。おそらく、礼拝での聖書朗読を配慮しているのであろう。
今日の聖句、新共同訳は面白い。「あなたの仰せによりすがらせ、命を得させてください。わたしの望みを裏切らないでください」「よりすがらせ」、「裏切らないでください」。詩人は謙遜を超えて、もう「卑下」の状態である。私たちの信仰とはそんなものだろうか。口語訳では、「あなたの約束にしたがって、わたしをささえて、ながらえさせ、わが望みについて恥じることのないようにしてください」。ついでに協会訳を開くと、「私が生きていけるように、あなたの仰せに従って私を支えてください。自分の望みについて、私が恥じ入ることがないようにしてください」と、見事に文語訳、口語訳を回復している。これなら、私たちの許容範囲である。
2019 日々の聖句 1月28日㈪
歓喜(よろこび)と救いとの聲は正しき者の幕屋にあり。主の右の手は勇ましき動作(はたらき)をなしたまう。主の右の手は高く上がり、主の右の手は勇ましき動作(はたらき)をなしたまう。(詩118:15~16)
汝ら常に主にありて喜べ、我また言ふ、なんぢら喜べ。(フィリピ4:4)
私の黙想:
この短い聖句に、「右の手」という言葉が3回も繰り返されている。これはどの訳でも同じである。特に主の右の手は「勇ましい」という言葉が2回繰り返されている。ここで用いられている「動作」を「はたらき」と読むのには、現代語では違和感がある。しかしそれが明治・大正時代の言葉なのであるから仕方がない。
「右の手」、神に右も左もあるのか、疑問は残るが単純に考えて、力強さの象徴であろう。
神が動けば、神は意味なしに動くことはないし、動けば何かが起こる。
この言葉口語訳では率直に「働き」、新共同訳では「御力」、協会訳では単に「力」と訳している。この差異は面白い。力とは発揮されて働きとなるが、働かなくても力は力である。
2019 日々の聖句 1月29日㈫
イスラエルの企望(のぞみ)なる者、その艱(なやめ)るときに救うたまう者よ、汝いかなれば此地に於て他邦人(ことくにびと)のごとくし、一夜寄宿(ひとりやどり)の旅客(たびびと)のごとくしたまうや。(エレミヤ14:8)
今われらは鏡をもて見るごとく見るところ朧(おぼろ)なり。然れど、かの時には顏を對(あわ)せて相見ん。(1コリント13:12)
私の黙想:
ここでは「他邦人(ことくにびと)」という珍しい言葉が出てくる。通常は「異邦人」である。時間の関係で「他邦人」という言葉と「異邦人」という言葉との詳細について調べていない。ただ、残念ながら口語訳以降は使われていない。
口語訳は「異邦の人」、新共同訳では「この地に身を寄せている人」と訳している。
そこで、私なりに勝手に考えると「異邦人」と「他邦人」とは確かに違いがある。日本語でも「異国人」「外国人」おまけに「ガイジン」といういい方もある。人間と人間との関係おいて、「異」と「他」、あるいは「外」との違いは何か。その説明は不要であろう。
協会訳で「希望」が文語訳では「企望」という漢字が当てはめられているのは面白い。これは単なる希望ではなく、その希望そのものを「企画」している者という意味であろう。その神がイスラエルにおいて「ガイジン」のような在り方をしている。
1月20日から始めた文語聖書によるローズンゲン、ちょうど1週間です。ぜひ皆様方のご意見をを伺いしたいと思います。
2019 日々の聖句 1月30日㈬
主は我儕(われら)を、御心に記(と)めたまえり。(中略)われらを惠みたまわん。(詩115:12)
汝らの名の天に録されたるを喜べ。(ルカ10:20)
私の黙想:
新共同訳ではかなり長い文章を短縮しているので、文語訳でも短縮しておく。「御心に記(と)め」を新共同訳、口語訳では「み心に留め」、協会訳では「思い起こし」、ほとんど同じようでないか違いがある。
これらの言葉を比較しながら、ルカ福音書の十字架上のイエスの言葉を思い起こす、というより心に留める。共に十字架上にいた悪人の一人が「イエスよ、あなたの御国にいらっしゃれたら、私のことを思い出してくださいますように」(23:42、田川訳)、これに対するイエスの言葉は省略しておく。これを文語聖書では「イエスよ、御国に入り給うとき、我を憶え給え」。
「み心に留める」「思い起こす」「思い出す」は、聖書を読む場合の鍵となる単語である。
2019 日々の聖句 1月31日㈭
妄(みだ)りに言を出し、劍をもて刺が如くする者あり。されど智慧ある者の舌は人を癒やす。(箴言12:18)
また船を見よ、その形は大(おおき)く、かつ激しき風に追はるるとも、最小(いとちいさ)き舵にて舵人の欲するままに運(まあ)すなり。斯くのごとく舌もまた小(ちいそ)きものなれど、その誇るところ大なり。視よ、いかに小(ちいさ)き火の、いかに大なる林を燃すかを。(ヤコブ3:4~5)
私の黙想:
新共同訳では、「軽率なひと言が剣のように刺すこともある。知恵ある人の舌は癒やす」。協会訳は解説の文章のようである。「あたかも剣で刺すかのように軽率に語る語る者がいる。知恵ある人の舌は癒やしを与える」。
この格言、このようにも言えるのではないだろうか。「軽率なひと言は人を殺し、知恵ある言葉は人を生かす」。少々、投げやりな黙想。仕方がない。
2019 日々の聖句 2月1日㈮
我が王よ、我が神よ。 我が號呼(さけび)の聲を聞きたまえ。我、汝に祈ればなり。主よ、朝(あした)に我が聲を聞き給わん。我、朝(あした)に汝の為に備えして俟望むべし。(詩5:2~3)
我、信ず、信仰なき我を助け給え。(マルコ9:24)
私の黙想:
2月初めの聖句は、まさに現在の私の祈りである。「明日を俟つ」。読み方によっては、主ご自身の応答に起き超える。「我、朝(あした)に汝の為に備えして俟望むべし」。
口語訳、「主よ、朝ごとにあなたはわたしの声を聞かれます。わたしは朝ごとにあなたのためにいけにえを備えて待ち望みます」。
新共同訳、「主よ、朝ごとに、わたしの声を聞いてください。朝ごとに、わたしは御前に訴え出てあなたを仰ぎ望みます」。
協会訳、「朝が来る度に、あなたに向かって身を整え、待ち望みます」。
祈祷書訳、「主よ、朝ごとにあなたはわたしの祈りを聞き、・・・・」。
2019 日々の聖句 2月2日㈯
汝、踴躍(おどり)をもて、我が哀哭(なげき)に変え、我が麁服(あらたえ)を解き、歓喜(よろこび)をもて我が帶としたまえり。(詩30:12)
その中の一人、おのが醫されたるを見て、大聲に神を崇めつつ歸り来たり。(ルカ17:15)
私の黙想:
「麁服(あらたえ」とは「荒妙」とも書き、粗い布織りの粗末な着物を意味する。この聖句を新共同訳では「あなたはわたしの嘆きを踊りに変え、粗布を脱がせ、喜びを帯としてくださいました」。
この詩はダビデが宮殿の建立式で歌ったとされる。「麁服」が質素の宮殿を意味し「帯」が新しい宮殿を象徴するのであろう。
紀元前1000年頃、ダビデが王位に就いたときに、この地方を支配するために有利な場所として名もなき丘の上に砦のような粗末な基地を造り、拠点とした。それが元々のエルサレムである。それはまさに「前線基地」に過ぎなかった。ダビデの地位が確立するに従って「エルサレム」は人口も増え、立派な都になった。そのときダビデは粗末な砦を改築し宮殿とした。